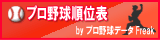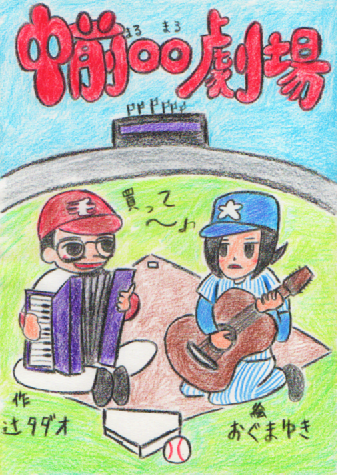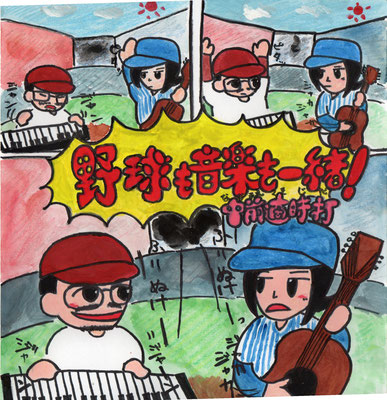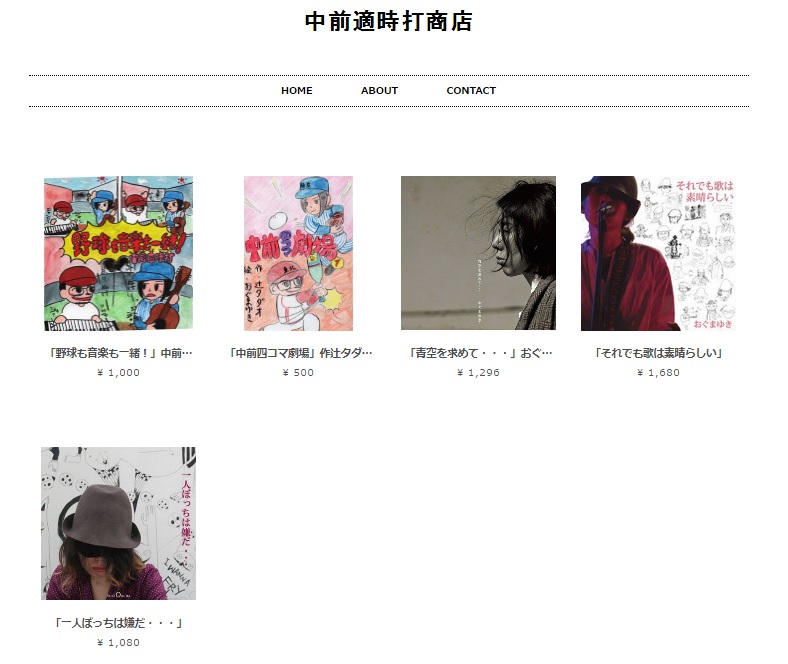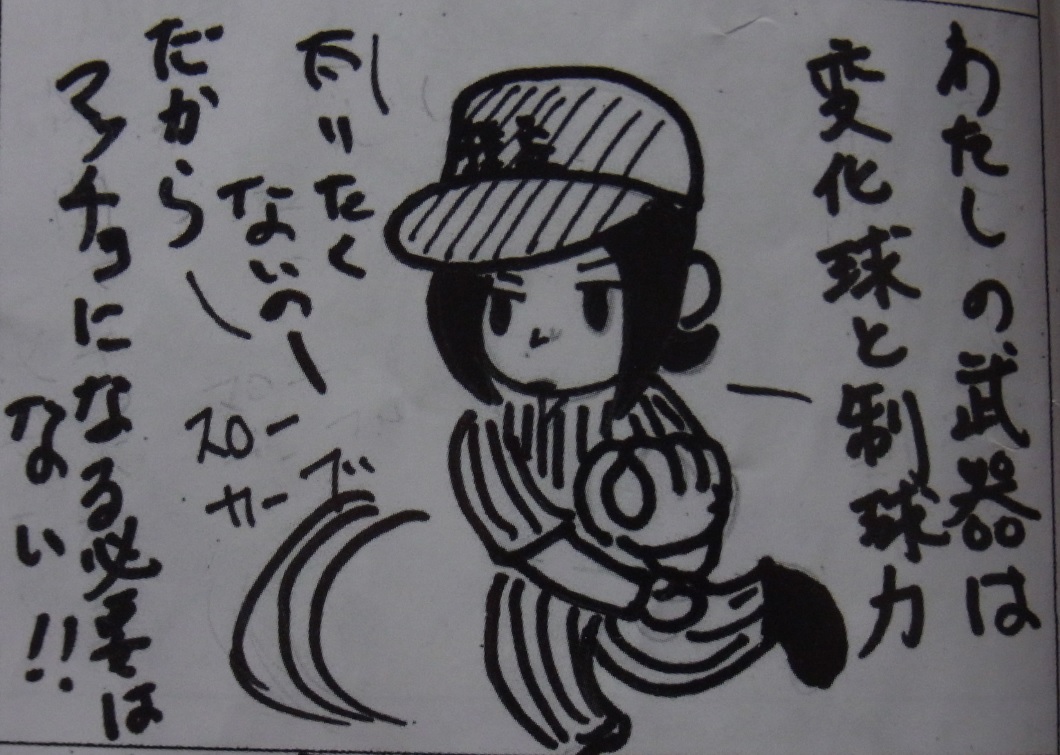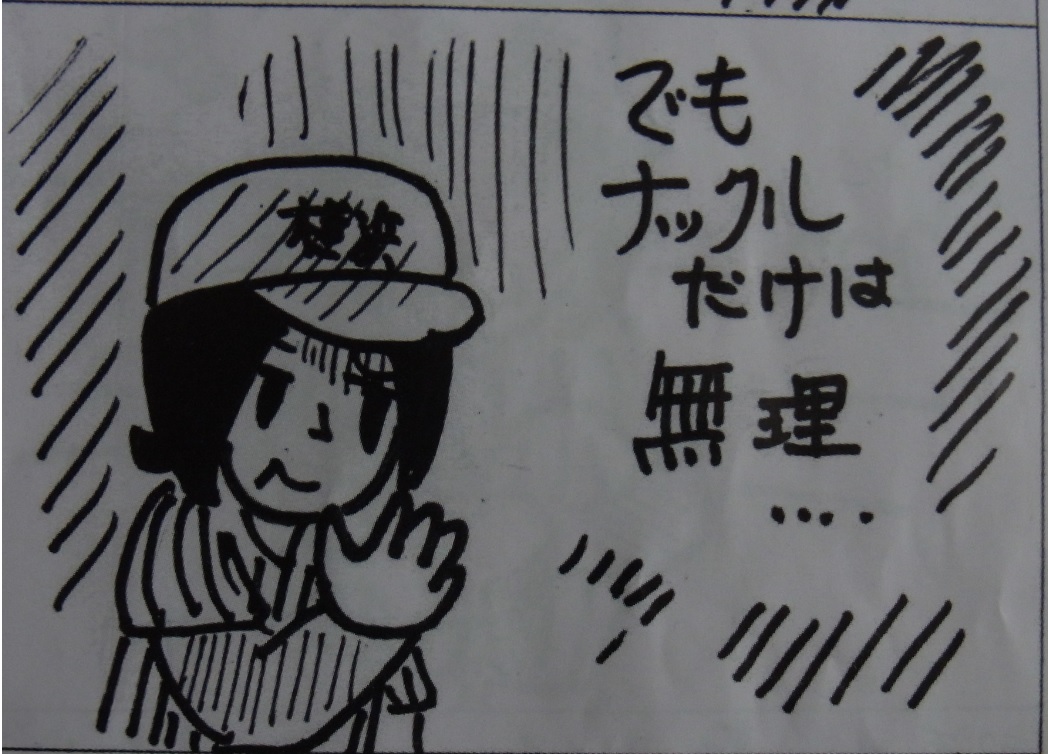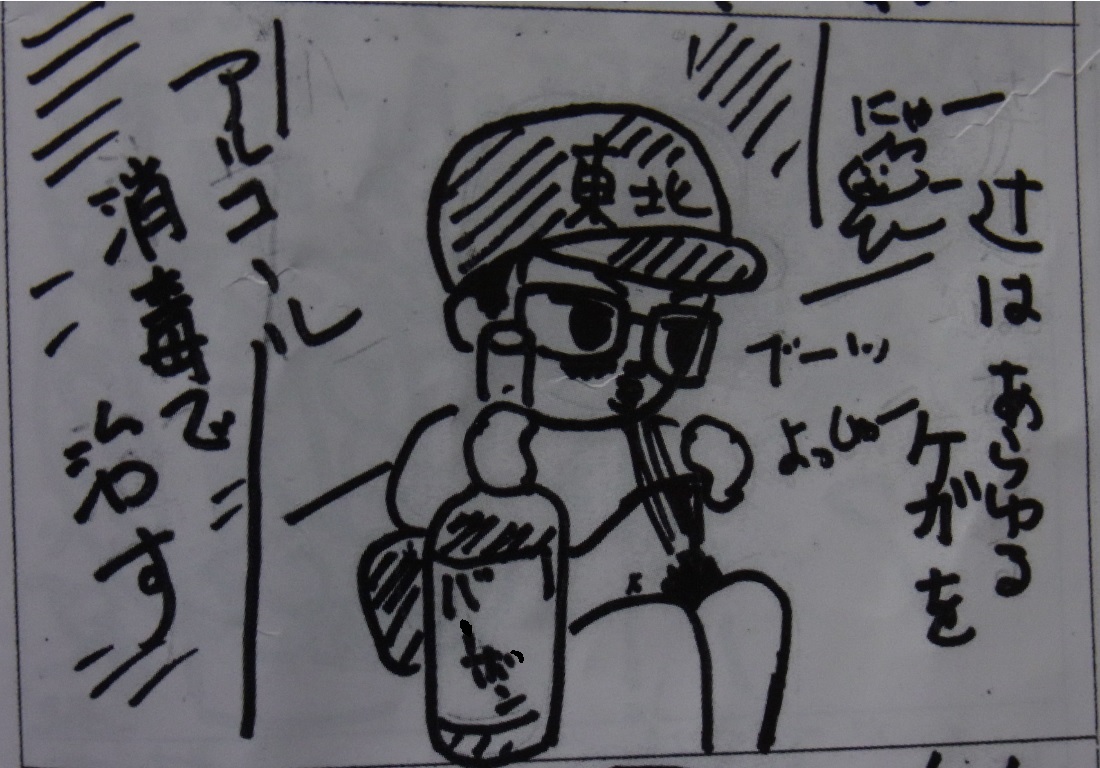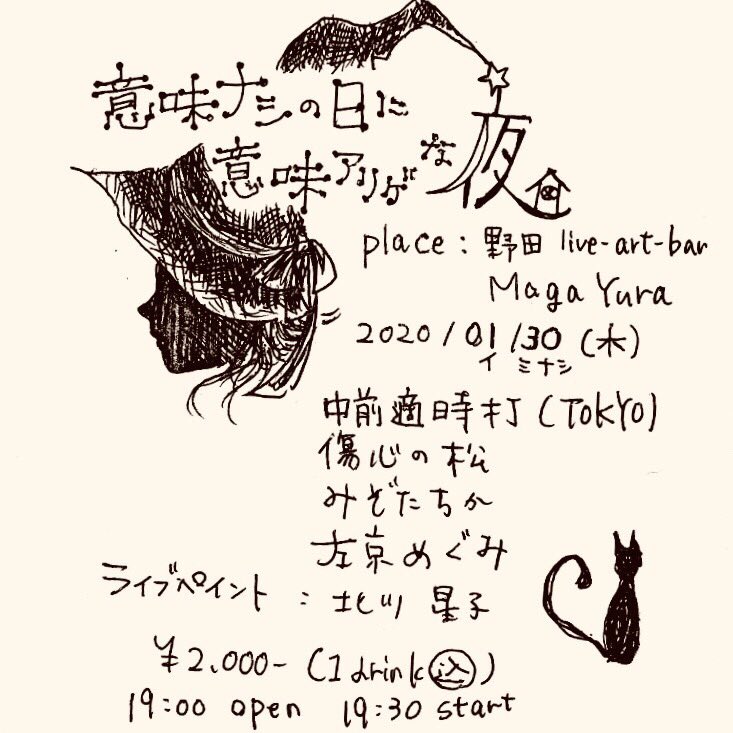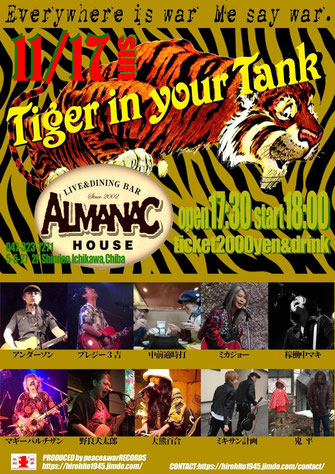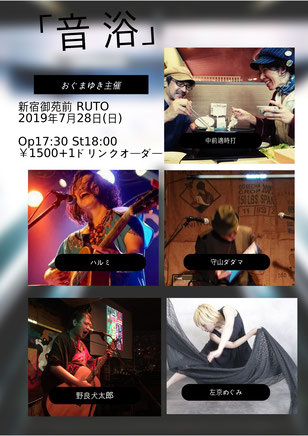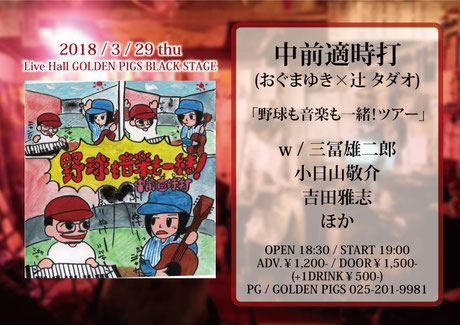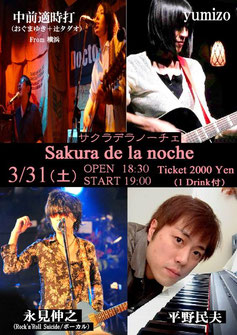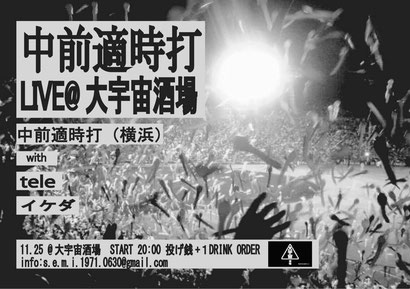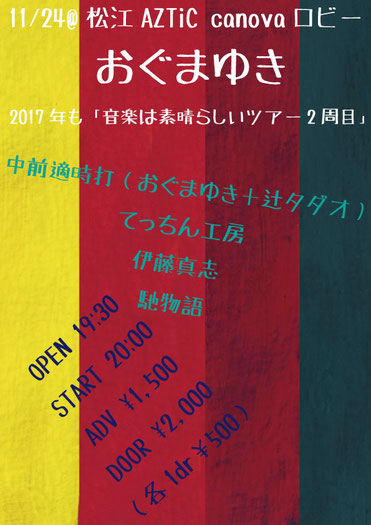Q1. これまで著作権料がいらなかったBGMに、なぜこれからは必要になるのですか?
A1. 音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても区別せずに著作権が及ぶのは国際的にはあたり前のこととされています。
ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、音楽喫茶など特別な場合だけでした。「録音物の再生演奏」に権利が及ばないということは、明らかに国際条約違反だとする海外からの指摘もあり、1999年6月の国会でこの規定の廃止され、権利が認められたからです。
ってことでその
「1999年6月の国会」
ってやつの詳細を把握してないんですけど
そうゆうところは抜きにして
ザクッと言えば、
「国際的に当たり前のこと」
なんてなことを
気にしないでいれば
「BGMに独自性を持たせたい商業施設」の方々が
未来永劫「CD購入の顧客」でありつづけてくれた
かもしれなかったのに・・・
みたいなね。
であと疑問なのは「1999年6月」
とかだったら
現在の「CD不況」に比べれば
全然ましな状況だったように記憶しますが
なんでそのタイミングでこうゆうことをするのか
いまとなっては疑問ですね。
さてなんでいま急に
これに触れるのかというと
「店舗BGMにCDをガンガン使ってた時代」
の記憶が生々しく残っているからなのです。
前に何度か書いたかもしれませんけど、
「いままさにどのCDを再生するか?」
で店舗スタッフ同士で
かなりギスギスしたりなんかして(笑)
そりゃそうですよ。
「単調な接客業務」
をやり過ごすにあたり
「BGMが自分の趣向に合うか否か」って
意外にデカいですからね。
好きな「アルバム」だったら
それこそ「ヘビーローテ」で
3回リピートでも全然OKで
おかげでなんだか仕事が早く終わった感でいっぱい!!
みたいなね。
ということで
私も「BGMでかけるCD選択闘争」にそこそこ参戦しました(笑)
邦楽から洋楽まで
ジャンル問わず幅広く試した結果
「最も就業時間が短く感じたCDナンバー1」
は
リッチブラックモア&レインボウ
の
「バビロンの城門」
でした。
わたくし特に
「ハードロックorヘビメタ」オタク
ではないのですが。
このアルバム
全部聞いても
確か40分そこそこなんですけど
単調なようでいて
意外に起伏もあり
しかしハードロックらしい景気のよさもある!
みたいな。
でわたしはそんな感じでしたけど
「ドリカム命女子」
とか
「森高命男子」
とか
いろいろな人が
自腹で購入したCDをお店に持ってきてました。
というようなことを鑑みるに結果から見れば
「国際的に当たり前のこと」規準で
自国のCD購入需要を積極的にしぼませたって
そりゃあんた「責任者出て来い!」って話なわけですよ。
まあ出てこないでしょうし、
時代も流れて
その他の要因もからんで
「CD不況」はもう
どうしようもないんだろうと思います。
思いますが、
「音楽」そのものは
無くなりはしないでしょうから
特に何も悲観はしておりません。